インボイス制度
050-3000-0768
【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)
050-3000-0768
【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)
2023/3/27
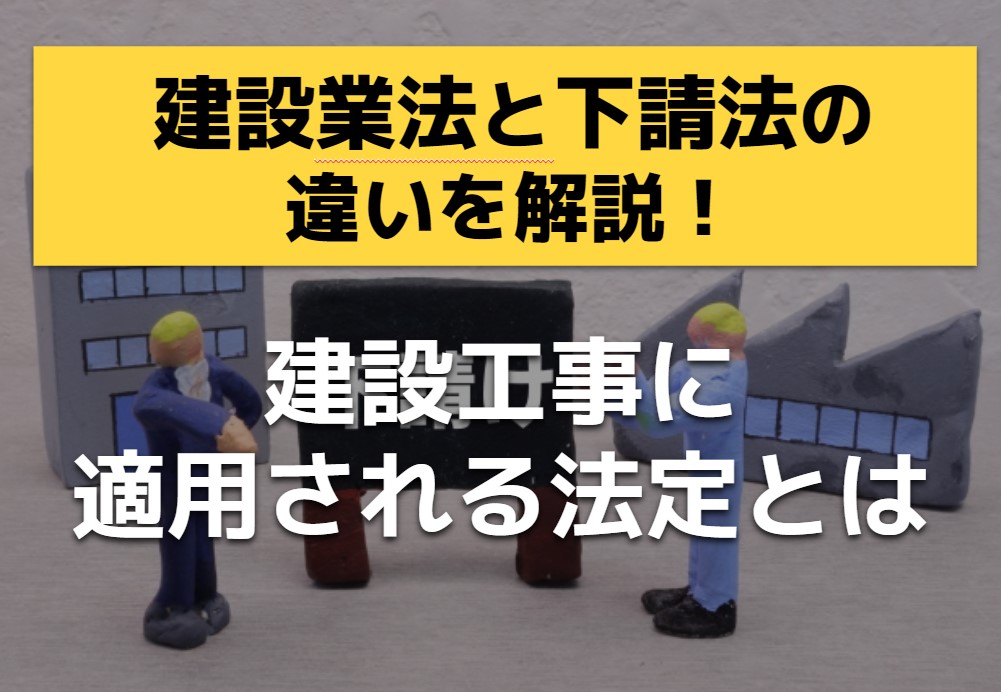
建設業・建築業界において、不当な取引を避けるためには法令を理解することが大切です。特にパワーバランスが大きく異なる建設業者・建築業者の間では、発注業者(元請負人)が受注者(下請負人)に工事をすべて行わせ、手数料だけを受け取ろうとする「丸投げ」や、下請業者への支払い遅延などが問題となっています。
このような不当な取引から下請業者を守るために制定されたのが、「建設業法」と「下請法」です。しかし、この2つの法律について、違いがよくわからず疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業法と下請法の違いについて解説します。2つの法律が適用される条件を把握して、トラブルになって弁護士事務所の先生に相談しなくて良いように、しっかりと学んでいきましょう。
建設業法と下請法の違いは、一言でいえば「建設工事の取引に関する法律かどうか」ということです。取引の当事者となる企業や法人・個人の、営んでいる業態に関係なく、取引の内容によって適用される法律が決まります。
| 建設業法 | 下請法 | |
| 建設工事 | ◯ | × |
| 物品の製造委託 | × | ◯ |
| 修理委託 | × | ◯ |
| 情報成果物の作成委託 | × | ◯ |
| 役務提供委託 | × | ◯ |
そもそも、建設業法と下請法は内容面で大きな違いはありません。どちらの法律も契約に関する取り決めを明確にしたものであり、規模の小さい業者を守るためのものだからです。
しかし、下請法では、取引をする業者の規模と取引内容ごとに条件が定められています。その中に建設工事に当てはまる条件はなく、建設業の下請となる業者は不利益を被る恐れがありました。そのようなリスクを回避するための法律が建設業法、ということになります。
大まかな内容と方向性に変わりはないものの、それぞれに細かい違いがあるので、該当する部分を確かめましょう。
| 建設業法 | 下請法 | |
| 契約内容の書面化義務 | 請負契約の当事者双方の義務 | 発注者のみの義務 |
| 受領拒否の禁止 | 元請業者の受領・検査義務 | 親事業者の受領義務のみ |
| 支払い遅延の禁止 | 元請業者が代金・費用の支払い後1ヶ月以内に、下請への支払い義務 | 親事業者が支払い期日までに下請代金・費用を支払う義務 |
| 買いたたきの禁止 | 「通常必要と認められる原価に満たない金額」を請負代金・費用とすることを禁止 | 「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金・費用の額」を下請代金・費用とすることを禁止 |
| 資材等の購入強制の禁止 | 適用される時期は「請負契約の締結後」に限定 | 適用される時期の限定はなし |
建設業法は、建設工事に関して契約のルールを定めた法律です。制定の背景には、建設業・建築業界において、業者ごとのパワーバランスに大きく差があるという特性がありました。
建設業者や建築業者の取引では、大規模な工事を請けた発注者(元請負人)が、その工事の一部または全部を受注者(下請負人)に委託することがあります。このとき、発注者(元請負人)の規模が大きいと受注者(下請負人)は委託を断りづらく、不当な工事でも受けなければならないという問題もありました。
このような不当な取引を持ちかけることができないように規制し、立場が弱い建設業者・建築業者を保護するのが、建設業法の大きな役割です。
建設業法については、建設業法令遵守ガイドライン(第8版)を参照するとより理解が深まるでしょう。
建設業法における下請契約とは、受注者(下請負人)とそれ以外の建設業者・建築業者間の取引についての契約についての取り決めです。下請法とは異なり、企業規模に関係なくこの規定が適用されます。
建設業法では、発注業者(元請負人)に対して以下の義務を定めています。
発注業者(元請負人)が請け負った工事を、手数料を受け取ることだけを目的として受注業者(下請負人)にすべて行わせる形で委託することを禁じている規定になります。建設工事では、大規模な工事となった場合に、受注者(元請負人)が工事の全部を受注者(下請負人)に委託するという契約を締結することがあります。受注者(下請負人)は発注者(元請負人)に比べて規模が小さく、取引数も小さい傾向にあるため、不当な契約を断るのが難しい場合があります。これを保護するために、丸投げ工事を禁止しています。
建設工事の代金・費用は、「通常必要と認められる原価に満たない金額」を請負代金・費用として委託することはできません。不当に安い金額での委託を防ぐものであり、弱い立場にある下請業者を守ると同時に、工事の品質を保つ目的もあります。
なお、建設工事の請負契約においては、諸費用を下請の代金・費用から差し引く「赤伝処理」という処理を行うことがあります。建設業法では、この赤伝処理について、明確に記載している文言がありません。しかし、不当に低い請負代金・費用の禁止などの条文で記載されている通り、工事代金・費用は適切なものにしなければならないという規制が行われています。
受注者(下請負人)に工事を委託した場合、工事終了後に検査を行う義務があるのは発注業者(元請負人)です。工事後に検査を行わないと、受注者(下請負人)は工事代金を受け取れないほか、工事の保管責任や危険負担を長期に渡って背負わなければなりません。これを防ぐために、発注者(元請負人)に対して受注者(下請負人)の工事が終了した後の速やかな検査義務を設けているのです。
なお、建設業法が適用されるのは取引内容が「建設工事」の名目である場合に限ります。建設業許可事務ガイドラインについてによると、建設業法の対象となる建設工事は以下の29種類があります。
上記に当てはまらない取引の場合、下請法の適用となります。
下請法は、取引内容ごとに関わる業者を資本金の規模で分類し、「親事業者」と「下請業者」を定義した法律です。親事業者に対して、取引の進行や支払いに関する義務と禁止事項を定めています。
下請法で定める取引は、主に以下の4つです。
まずは取引内容ごとの、資本金による業者の分類を理解しましょう。
以下の表で、下請法の対象となる取引内容と事業者の定義をまとめました。
| 親事業者 | 下請業者 | |
| 物品の製造委託 | ・資本金3億円超えの法人で、個人または資本金3億円以下の法人に製造委託等をする事業者 ・資本金1,000万円超え3億円以下の法人で、個人または資本金1,000万円以下の事業者に製造委託等をする事業者 |
・個人または資本金3億円以下の法人で、資本金3億円超えの親事業者から製造委託等を受ける事業者 ・個人または資本金1,000万円以下の法人で、資本金1,000万円超え3億円以下の親事業者から製造委託等を受ける事業者 |
| 修理委託 | ||
| 情報成果物の作成委託 | ・資本金5,000万円を超える法人で、個人または資本金5,000万円以下の法人に情報成果物の作成委託または役務提供委託をする事業者 ・資本金1,000万円超え5,000万円以下の法人で個人または資本金1,000万円以下の法人に情報成果物の作成委託または役務提供委託をする事業者 |
・個人または資本金5,000万円以下の法人で、資本金5,000万円超えの親事業者から情報成果物の作成委託または役務提供委託を受ける事業者 ・個人または資本金1,000万円以下の法人で、資本金1,000万円超え5,000万円以下の親事業者から情報成果物の作成委託または役務提供委託を受ける事業者 |
| 役務提供委託 |
下請法では、親事業者に以下のような義務が規定されています。
下請法が定めるところの親事業者は、下請業者に対して委託を行った場合、契約に関する書面を交付する必要があると規定されています。
書面には、以下の内容を記載します。
上記事項の中で、正当な理由によって内容が定められないものがある場合、記載しなくても問題ありません。ただし、該当する内容が明確になった場合は、すぐにその内容を記載した書面を下請事業者に交付するものと定められています。
下請法においては、支払い期日は親事業者が定める義務となっています。下請事業が行った取引の内容については検査の有無を問わず、法令で決められた期間内に支払い期日を決定しなくてはなりません。
法令では、「親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない」と規定されています。
下請法では、委託を行った親事業者に対して、書類の作成と保存を義務付けています。この書類に記載する内容は以下の通りです。
親事業者は、上記内容を記したものを、紙面または電子データで保存しないとこの法律に違反することになります。
委託した取引の費用の支払いが遅延した場合の処分についても、下請法で定められています。下請代金・費用の支払期日までに下請代金・費用を支払わなかったときは、遅れた分の日数に応じて利息分を支払わなくてはなりません。この時の遅延利息については、公正取引委員会が割合を定めています。
このように、親事業者(建設業者・建築業者の場合は元請)に対して、下請の取引についての義務を定めることで、下請業者の保護を行っているのです。
建設業法と下請法の違いについて、ここまで解説してきました。しかし「うちは建設業者・建築業者をやっているから、建設業法の適用なんだな!」と捉えている人がいるかもしれません。これは大きな誤解です。
建設業法や下請法は、取引内容によって適用される法律が変わります。建設業法はあくまで「建設工事の取引」の場合に適用されるものであり、取引を行うのが建設業者・建築業者だからといって、建設業法が適用されるとは限りません。
例えば、建設業者・建築業者が建設工事を請け負い、その工事を下請に委託する場合は、建設業法の適用となります。しかし、物品の製造や修理などを委託する場合は、建設業法ではなく下請法の適用となります。下請法の適用となる場合、取引内容や資本金などから下請業者に当てはまるのかを確認しておく必要があります。
このように、建設業法と下請法は取引に関わる業者が営んでいる業態にかかわらず、取引内容によって適用される法律が決まります。名前が似ていてややこしいですが、取引のトラブルを避けるために、どちらの法律が適用されるのかを正しく理解しておきましょう。
建設業法と下請法には、以下のような違いがあります。
法律の内容や方向性については大きく変わることはないものの、細かな違いが存在する部分もあります。請け負っている取引が建設工事なのか、それ以外なのかを確認し、適用される法律を把握できるようにしておきましょう。
また必要なものは発注者(元受追人)でも、発注者(下請負人)でも大切なことなので、契約書をしっかりと締結をするようにしましょう。契約書はWEB検索をして、無料でオンラインで取得できるものを使用するのも良いですが、トラブルを避けるうえでも、まずは普段お取引されている弁護士事務所の先生に相談してみてください。
今回の解説は以上となります。