050-3000-0768
【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)
050-3000-0768
【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)
2025/6/3
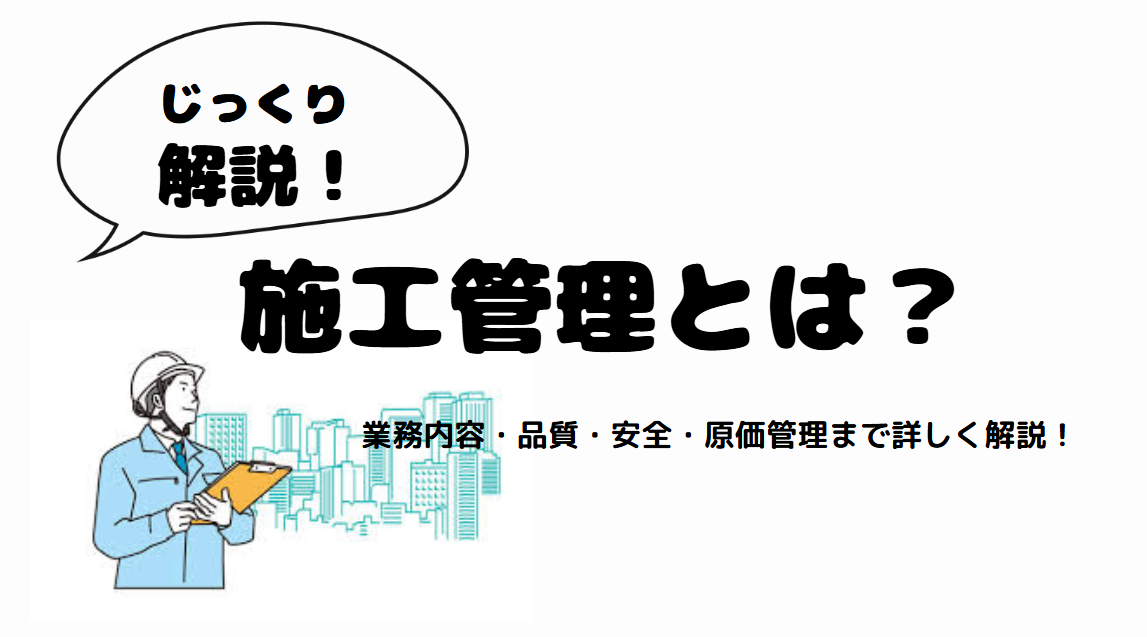
建築業に欠かせない施工管理。
「安全第一、品質第二、生産第三」をどの業界よりも重視したい建設業と直結するのが施工管理業務と言えます。
今回は、
「ちゃんとできているか不安だな…」
「マネジメントや書類に関して、自信が無い…」
などのお悩みを抱えている方向けの記事になっております!
内容は多岐にわたりますが、ぜひ最後までご覧ください!
施工管理とは、建設工事で、工程や計画・安全などを管理し、指揮・監督する役割です。
「セカコン(Second Contractor)」とも呼ばれます。
安全で品質の高い建物を予算内・工期内で完成させることが目的です。
工事を行う前の、施工図や工程表の作成、現場作業員の手配、資材発注から、
工事着工後の監督まで担う、
業務内容が多岐にわたる仕事です。
また、担当領域は工事内容によって変わってきますが、
主に以下の4つの管理業務が主要なものとして挙げられます。
先ほど「セカコン」と出てきましたが、似ている言葉で「ゼネコン」というものがあります。
何が違うのでしょうか?
「General Contractor(ジェネラル・コンストラクター)」の略称がゼネコンで、
総合建築業者を指します。
元請業者として、発注者から建築・土木工事を請け負います。
そして、それを振り分けて仕事をそれぞれ依頼するのですが、
その依頼先が、専門業者である「サブコン」なのです。
売上高や規模の大きさによって、
スーパーゼネコン、準大手ゼネコン、中堅ゼネコンに分類されます。
施工管理を担う人たちは主に
安全・品質・工程・原価の4分野を管理します。
独立しているように思われるかもしれませんが、実は密接な関わりがあるのです!
それぞれの管理の目的と業務内容を解説します!

建設現場において安全な環境を整える業務です。
怪我人や死亡者が出やすい現場で、工事を無事故で終えるためには最も欠かせない業務の1つです。
具体的な仕事内容をいくつか紹介させていただきます!
使用する機器や機材の安全点検を行います。
これを怠ると、最悪の場合、重大な事故に繋がってしまいます。
機器の故障で作業が滞ってしまったり、
誤作動に作業員が巻き込まれてしまう事故などを防ぐためにも欠かせない業務の1つです。
「どうしてこれが安全に関わるの?」と思った方はいませんか?
体調不良の状態で作業を続けるのはとても危険です。
ましてや常に危険と隣り合わせの工事現場ではなおさら危険です!
体調不良は注意力の散漫、動作の緩慢に繋がり、事故の危険性も高まります。
作業員の安全を確保し、かつ工程を円滑に進めるためにも健康チェックは欠かせません。
5Sとは「整理・整頓・清掃・清潔・躾」のイニシャルをとったものです。
これらを徹底することで、業務効率の向上や生産性の向上、
安全性の向上、従業員のモラル向上などの様々な効果を期待することができます。
例えば、不要なものを排除して、必要なものだけにすると、
作業員全員が資材や工具の位置を把握しやすくなり、
作業のスペースが広がったりとメリットが次々出てきます!
ヒヤリハットを共有することで、現場に「注意しなければいけない」という意識が芽生えます。
安全意識と事故発生率は反比例の関係にあります。
実際に起こった事例を共有して、作業員の安全意識を高めましょう。
現場全体で協力して取り組むことで、円滑に工事を進められますし,
品質維持のためにも重要な活動です。
訓練を定期的に実施し、常に安全を意識する現場づくりを心がけましょう。

建設工程が、設計計画通り・仕様書の通りに進んでいるかを管理する業務です。
撮影するのは、
など、他にもたくさんあります。
国土交通省が、平成25年3月に発行した『写真管理基準(案)』や、
その他整備局が出している、「品質管理写真撮影箇所一覧表」などを確認してみてください!
建設現場では、様々な品質管理を行われています。
例えば、コンクリート関連の試験では、
①圧縮強度試験 :コンクリートのHん室を左右する最も重要な試験です。
現場で採取したコンクリートでテストピースを作成し、材齢28日で圧縮強度を測定。
これにより、構造物の安全性を保証します。
②スランプ試験 :コンクリートの流動性(柔らかさ)を測定する試験です。
スランプコーンという器具を使って、コンクリートの沈み具合を測定。
③塩化物含有量試験 :コンクリート中の塩化物イオン量を測定。
鉄筋の腐食を防ぐための重要な試験で、海水の影響を受けやすい地域では特に重視されます。

工期内での完成を目標にスケジュールを管理する業務です。
現場の職人などの工事に関わる人員の配置やスケジュール調整、工事で必要な重機の手配を行うのが、業務内容です。
工程管理では、場面に応じて様々な工程表を使い分けることが重要です。
横軸に時間、縦軸に作業項目を配置するため、各作業の開始終了時期が一目で分かる、
最も一般的で理解しやすい工程表です。
全体工程の概要把握、発注者や関係者への説明、工程会議などで活躍します。
作業間の依存関係を矢印で表現するので、クリティカル(最短工期を決定する経路)が明確になります。
工程の最適化に有効です。
複雑な工事の工程検討、工期短縮の検討、遅延の影響分析にも使用されます!
1週間単位の詳細な作業計画を立て、日々の作業内容と責任者を明記します。
短期的な調整に最適な工程表です。
日常的な作業指示、作業員への具体的な指示、短期的な工程調整などで使用されます!

工事にかかる費用などを正確に計算し、管理をすることで、コストの削減や利益の確保を行う業務です。
建設業における原価の扱いについてですが、建設業における総原価とは、
材料費・労務費・外注費・経費から成る工事原価に販売費・一般管理費を加えたものです。
営業外費用や特別損失などは、非原価項目ですので、要注意です!
が該当します
などが該当します。
などが該当します。
などが該当します。
施工管理の仕事は、資格がなくても行うことは可能ですが、
「収入を増やしたい!」「実力を証明したい!」などとお考えの方に考えていただきたいのが資格 です!
施工管理に関わる資格はいくつかございますので、紹介させていただきます。
建設業法第27条において技術検定を行う、国家資格の1つです。
工事の分野や内容によって、7つに分かれています。
資格の取得後には
になることができます。
2級と1級が準備されており、
それぞれなることができます。
(出典:一般財団法人 建設業振興基金 施工管理技術検定 https://www.fcip-shiken.jp/)
1級を取得することで、2級では携われなかった仕事も行うことができるようになります!
建築士法に定められた資格で、建物の設計・工事の管理を行う技術者です。
資格は、国家試験や知事試験により、国(国土交通省)や都道府県から与えられます。
1級建築士、2級建築士、木造建築士に分けられます。
木造建築士、2級建築士、1級建築士の順に扱える建物が増えていきます。
(出典:一般社団法人 東京建築士会 https://tokyokenchikushikai.or.jp/index.html)
技術士法に基づいた、
科学技術に関する技術的専門知識と口頭の専門的応用能力及び豊富な実務経験を有し、
公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた、優れた技術者の育成のための国家資格です。
文部科学省所管の資格になります。
建設業界だけでなく、航空業界など、部門がたくさん設けられています。
施工管理に関わってくるものは、
建設部門、資源工学部門、電気電子部門、上下水道部門などです。
(出典:公益社団法人 日本技術士会 https://www.engineer.or.jp/contents/about_engineers.html)
ここまでの資格の紹介を表にまとめました。
| 資格名 | 管轄省庁 | 目的 |
| 施工管理技士 | 国土交通省 | 建設工事の適切な施工を確保し、公共の福祉に寄与する |
| 建築士 | 国土交通省 | 建築物の設計や工事監理を適切に行い、安全で高品質な建築物を実現すること |
| 技術士 | 文部科学省 | 科学技術に関する技術的専門知識と口頭の専門的応用能力及び豊富な実務経験を有し、公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた、優れた技術者の育成のため |
ご自身の職業やキャリアに応じた資格を是非取得してください!
さまざまな法律と関係を切ることができない建設業。
管理職に就かれている方だけでなく、建設業に携わるすべての方に知っていただきたい!
建設業に関する多くのルールを定めた法律です。
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることで、
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、
建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
(出典:e-GOV 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100)
建設業法の対象となる工事は以下の通りです。
これらを超える工事の場合には、
建設業(あるいは特定建設業)の許可が必要になる場合があります。
また、先ほどの条件を下回る工事は「軽微な建設工事」として扱われるため、
建設業の許可は必要ありません。
その他にも
などが該当します。
建設業法にはほかにも、
などが定められています。
違反した場合は、営業停止などの行政処分や刑事罰などが定められています。
労働三法の1つです。
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」
と第1条に定められています。
労働基準法に基づき、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間と定められています。
これを超える場合には、36協定の締結と労使間の合意が必要になります。
施工管理は、建設業就業者の中でも特に残業が多い職種の1つです。
技術者の残業が月平均45時間以上の企業は、令和5年度の調査で14.9%でした。
(出典:国土交通省「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和5年度)」)
施工管理の仕事は、着工前から始まり、
調整業務や工程管理、作業者の指揮・監督などのすべてに関わるため、
残業が多くなってしまいがちです。
健康に働いてもらうためにも、ぜひ重視したい法律であると言えます。
ところで、先程出てきたこの言葉。
皆さん、ご存じですか?
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせる場合、
また法定休日(週に1日もしくは4週に4日)に働かせる場合に、
労使(労働者と使用者)の間で結ばれる協定です。
建設業界でも他の業界に負けず、さまざまな改革が行われています。
代表的なものを紹介します!
2019年から順次施行されていった、「働き方改革関連法」
休日の取得状況に関して、「4週8休」とする割合は、技術者では21%以上、技能者では25%以上に増加しました。
(出典:国土交通省「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和5年度)」)
また、2024年4月から時間外労働の上限規制が開始されました。
国土交通省が発表したガイドラインには、週休のことだけでなく、
があげられています。
インターネットの普及と高度化によって、さまざまなサービスが提供されています。
例えば、以下のことが行えるアプリなどが登場しています。
これにより、事務作業の軽減やコミュニケーションのずれ防止などが期待できます!
さまざまな会社から多様なアプリやサービスが提供されていますので、
御社にあったサービスを探していただいて、ぜひご活用ください!
ここまで、施工管理についてや、業務内容、施工管理に関わる資格や法律について解説しました。
工事に関わることを広く行う、忙しい業務にはなりますが、
成果が目に見える形で現れ、実際に人々の生活の役に立つ実感が得られるお仕事で、
頑張った分の達成感ややりがいが感じられるお仕事であると分かっていただけたのではないでしょうか。
建設業の需要や建築士の人気が高まりつつあります。
どんどん人手が増えて、個人が担うべき仕事量も変化していくでしょうが、
1人1人の働きやすさが確保できるといいですね。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
みなさまからの「参考になったよ!」の温かい声、お待ちしております!