050-3000-0768
【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)
050-3000-0768
【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)
2023/7/6
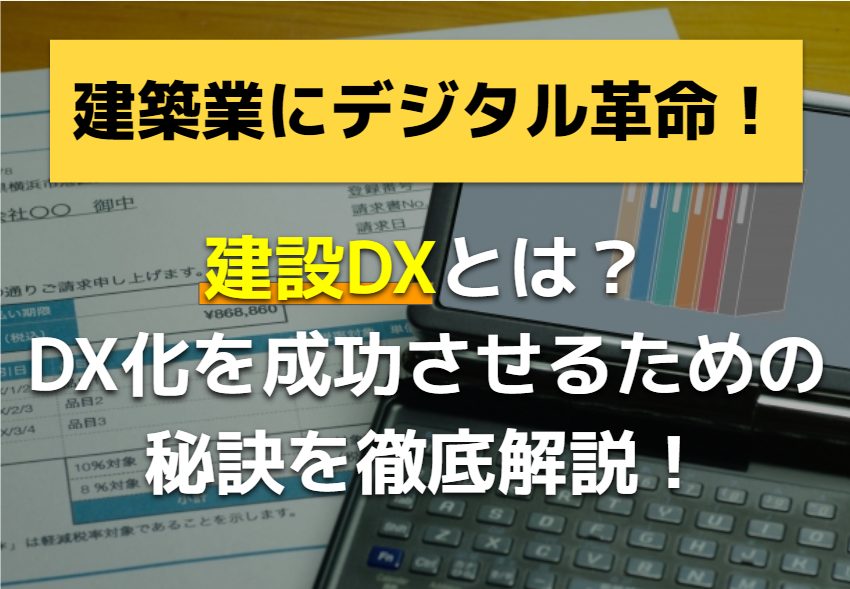
DXは、日本のあらゆる産業で注目されている取り組みです。
特に建設業界では、業務効率化や省人化を達成し、業界の問題を解決するための施策として
DXへの関心が高まっています。
しかし、DXがどのようなものなのかきちんと理解できていない人も多いのではないでしょうか。
DXについての理解が不十分だと、
せっかく導入しても無駄な投資となってしまうかもしれません。
この記事では、建設DXについて徹底的に解説します。
導入するメリットやDXの具体的な手順を理解して、効果的なDXを行いきましょう!
記事内でDXの取り組み事例を紹介しているので、そちらもぜひ参考にしてください。
建設DXとは、建設業界におけるDX化の取り組みのことです。
ただ建設業・建築業における取り組み、というだけで、他業種の場合と大きな違いはありません。
そもそもDXとは、「デジタルトランスフォーメーション(技術革新)」のことを指します。
デジタル技術を活用して、社会や生活の形・スタイルを変えようという取り組みのことです。
本来はビジネスの領域に限らず、社会全般の変革という意味で使われる言葉ですが、
ビジネス全般にDXが波及してきた近年では、
ビジネス用語として用いられる場面も多くなってきています。
建設業界においては、工事現場の管理や経理、施工管理などでDX化が進んでいます。
デジタル技術を用いて新たな組織を作り上げることで、これまでの様々な問題を解決し、
より生産性を高く、働きやすい環境を整えることがDX化の目的です。
建設DXが注目されるようになった背景には、以下の3つが挙げられます。
それぞれ見ていきましょう。
リモートワークの拡大
建設DXが拡大されている動きの背景には、リモートワークの拡大が挙げられます。
DX化を行うことによって、リモートワーク中心のスタイルへと移行し、
オンラインでのやり取りができるようにするのが現在の主流です。
建設業において、
顧客とのやり取りや社員同士のコミュニケーションは対面でのやりとりがほとんどです。
リモートワークに移行する場合、現場が混乱してしまうリスクも考えなくてはなりません。
DXを行えば、リモートワークの導入にも役立ちます。
変化する時代の波に乗るために、DXの存在が注目されています。
既存システムの老朽化・ブラックボックス化
建設DXが注目される背景には、
既存システムの老朽化やブラックボックス化が問題視されていることも挙げられます。
多くの企業が今使用しているシステムは、長い間使われてきているものも少なくありません。
代々受け継がれてきたシステムは、決まったやり方に則るだけで、簡単に技術を継承できます。
しかし、古くなったシステムは動作不良やセキュリティ面の低下など、無視できない問題も存在します。
さらに、長年使われてきたシステムがブラックボックス化していることもあります。
ブラックボックスとは、組織内部の仕組みがわからなくても使用できる状態のことを指します。
システムエラーを起こしたときに誰も復旧の仕方がわからない、というような状態に陥ってしまい、
最悪の場合は顧客に多大な迷惑をかけてしまうかもしれません。
このような問題があったとしても、「現状何も発生していないから大丈夫」と、
新しいシステムへの移行を考えない企業も少なくないでしょう。
既存システムへの依存状態から脱却できなければ、
2025年にはシステム障害やデータの損失が起こると考えられています。
その結果、年間最大12兆円もの経済損失が生まれる可能性があるとの指摘もなされています。
DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~
現在はエンジニアでなくてもシステムの仕組みを理解でき、
誰でもエラー発生時に対応できるシステムを使うことが推進されています。
DXによって多くの人が扱えるシステムを作れば、
より生産性の高い仕事ができるようになるでしょう。
人材不足
人材の不足も、DXが注目されるようになった背景のひとつです。
深刻な高齢化による単純な労働人口の減少に加え、
高いレベルの技術を継承する人がいないという問題も発生しています。
建設業の人材不足は、業界イメージが悪さが主な要因です。
仕事内容がきついのに給料は安い、などのマイナスイメージによって、
若手の世代は建設業を敬遠してしまいます。
現在の働き手も、待遇に不満を覚えて他業種へ転職してしまうことも増えてきました。
DXを活用すれば、業務効率化や省人化により、労働環境の改善が見込めます。
働きやすい環境が整えば、労働人口の減少に歯止めをかけるきっかけとなります。
人材を確保するという面からも、DXが注目されているのです。
建設DXには、数々のメリットがあります。
どのようなメリットがあるのかを正確に把握して、実際にDXを行うべきなのか検討してみましょう。
建設DXのメリットは、以下の5つが挙げられます。
業務効率化できる
建設DXの大きなメリットは、業務を効率化できることです。
建設業の業務は、大別すると以下のようになります。
上流工程では、例えば設計・測量を3Dデータで行えば、
手書きの図面を作る時間を大幅に短縮できます。
顧客との打ち合わせもオンラインで完結するうえ、
データでのやり取りで認識にすれ違いが生じることも防げるでしょう。
機械学習を活用すれば、下流工程の業務も一部自動化できることに期待が寄せられています。
人間が関わる部分を最小限にすれば、
労力を抑えられるだけでなくヒューマンエラーの防止にも役立ちます。
人的コストの削減になる
人的コストの削減になることも、建設DXの大きなメリットです。
業務効率化や自動化によって、人間の手を必要としない作業が増えていくでしょう。
結果、余分な人員をかけず、必要なコストを最小限に抑えることができます。
大規模な工事になれば、人的なコストは多大なものになります。
単純な作業を機械に任せる仕組みが整えば、
その工程に関わる人的コストを必要以上にかける必要はありません。
工事にかかる出費が多い建設業だからこそ、削減できるコストは削減できるようにしていきましょう。
省人化を実現し、人的コストを削減するためにも、DXの取り組みを行ってみてください。
技術継承をしやすくなる
技術を継承をしやすいという部分でも、建設DXは多いに役立ちます。
DXで様々な仕事を自動化・効率化すれば、
複雑な処理をしなくても機械の使い方をおぼえるだけで、簡単に技術を次の世代へと教えていくことができます。
建設業は高齢化による人手不足の状況にあり、技術の後継者が少ないことが問題となっています。
現場での技術継承は、熟練した技術者・職人の技を見て、経験する中で培われていく、というのが一般的な認識ではないでしょうか。
確かにスキルの習得は職人から教えてもらうことが大切ですが、一人前になるまでは長い年月を必要とします。
特にKKD(経験・勘・度胸)のような数値化しにくい能力は、多くの場数を踏まないと手に入らないものです。
DXを活用すれば、初心者でも同じように一定の技術を持てるようになります。
教育にかかっていたコストも大幅に短縮できるので、全体で見ればかなりのスピードでスキルを身につけられるでしょう。
もちろん、経験を積み重ねる大切さは無視できませんが、
DXで一定基準の技術を獲得してから現場で経験を重ねれば、従来よりも多くの経験値を得られるでしょう。
技術継承の観点からも、DXは大きな期待を寄せられています。
安全性が高まる
現場作業の安全性が高まるのも、建築DXのメリットです。
従来の現場作業は、ときに危険なことも人間がやらなくてはならない状況もありました。
どれだけ気をつけていても、ほんの少しの不注意や偶然により、
命を落としてしまうような大事故に繋がるリスクをゼロにはできません。
そこで建築DXでデジタル技術を取り入れれば、危険な場面は機械に任せる選択肢も取れるようになります。
危険なことをしなくても済むのは、会社にとっても労働者にとっても大きなメリットです。
大切な社員の命を守るためにも、DXを行うことを検討してみましょう。
他社との差別化になる
建設DXを行えば、競合他社との差別化を図れます。
都市部ではDXが進むものの、地方ではまだDXへの理解が進んでいるとは言い難い状況です。
しかし、顧客の立場では「オンラインに対応してほしい」「工事が早く終わるならそのほうがいい」などのニーズも考えられます。
いち早くDXを取り入れれば、まだDX化していない他社よりも優位に立つことができます。
早いタイミングでDX化していることをアピールすれば、
先行者としての利益を取れる可能性も高くなります。
逆に他の会社がDX化してしまえば、自社としてもDXを余儀なくされてしまうかもしれません。
DX市場のイスが空いているうちに、取り組みをアピールしてみるのもおすすめの手法です。
企業の価値を高める意味でも、DXを取り入れるメリットは大きいといえるでしょう。
建設DXとはどのようなものなのか、どんなメリットがあるのかを解説してきました。
実際にどのような技術があるのかを知りたい方も多いのではないでしょうか。
ここでは、建設DXで用いられるデジタル技術をそれぞれ紹介します。
自社の課題を解決できる技術を見つけて、導入の参考にしてください。
以下4つのデジタル技術を紹介します。
クラウドサービスとは、オンライン上でデータのやり取りができるシステムのことです。
オンライン環境にいればいつでもアクセスできるので、管理者と現場がリアルタイムで情報を共有するのにも役立ちます。
クラウドサービスには、以下の種類があります。
このうち、建設業・建築業で活用するならもっとも導入が簡単なSaaSがおすすめです。
SaaS以外の2つは自分でサーバーを立てる必要があることに加え、メンテナンスのコストがかかります。
データの共有のみを目的としてクラウドサービスを活用するなら、SaaSを使っておけば問題ありません。
SaaSの代表的なサービスには以下のものがあります。
BIM/CIM(ビムシム)
BIM/CIM(ビムシム)とは、「3次元モデルを活用した建設プロセス」のことです。
少しわかりにくい場合は、立体的な図面を作成できるデジタル技術のことだと考えておくとわかりやすいでしょう。
平面の図面を見るよりも、立体的な図面を見る方が建物の完成形のイメージを正確に捉えられます。
工事が始まってからの手戻りや仕様変更などを防ぐことにも効果的です。
人工知能(AI)
人工知能とは、コンピュータに学習を行わせる技術のことです。
データを蓄積させて様々な状況を経験させることで、最適な判断を返してくれるようになります。
建設業においては、図面をAIに描かせたり、映像データから現場の進捗を判断させたりなどの使い方が可能です。
人間と同様に学習を行わせることができますが、その吸収スピードは人間よりも格段に速いです。
AIに技術を覚えさせることもできるので、人間が関わらなくても済む工程が増えていくでしょう。
ICT(情報通信技術)
ICTとは、インターネットを介して連絡や機器の遠隔操作を行う技術のことです。
現場とオペレーターの間で遠隔のコミュニケーションをとれるようになれば、
リアルタイムでの情報共有が可能になり、連絡もスムーズです。
遠隔で機器を操作できるようになれば、危険な現場に人が出向くことなく施工を進められます。
ドローンのような機器を活用すれば、離れた場所にいても現地の情報を映像で確かめることができるでしょう。
建設DXは、以下の手順で行います。
導入フローを認識して、滞りなくDXを行えるように準備していきましょう。
まずは現状の課題を整理しましょう。
どんな業務にコストがかかっているのか、今後の経営でどんなことを不安に感じているのかが明確になれば、
活用すべきツールやシステムがわかるようになります。
現状把握を行うなら、現場の声を聞いてみるのがおすすめです。
不満を抱えたまま仕事をしている人がいるなら、それは早急に対処しなくてはなりません。
同じように不満を感じている人が多くいるなら、なおさら早く着手すべきです。
会社の問題点を洗い出して、どこを改善すべきなのかを把握しましょう。
問題が明確になったら、目的と戦略を考えるフェーズへと移行します。
DXによって会社がどんな状態になればよいのか、目的を考えましょう。
この目的をもとに、戦略を立案していきます。
ポイントとしては、上層部だけが変革を決めるのではなく、現場の声も取り入れることです。
目的がわからないままDXを進めると、
現場スタッフに不信感を抱かせる要因になってしまいます。
目的と戦略を明確にして、疑問の生まれない方向性を提示してあげるとよいでしょう。
目的と戦略が決まったら、DXの導入体制を整えましょう。
DXの導入体制とは、例えば以下のような準備があります。
DXにかかるコストは、かなり大きくなると思っておくべきです。
特にDXを扱える人材がいるかどうかは変革を成功させるための重大な要素となります。
人的資源と資金を上手にやりくりして、DXが成功する下地を整えましょう。
社内の環境が整ったら、実際にデジタル技術を導入して活用してみましょう。
この記事で紹介した通り、建設DXに用いられるデジタル技術は様々な種類があります。
しかし、すべての技術を導入するのはよい方法とはいえません。
まずは最低限必要なものを選択して、少しずつDXを行っていきましょう。
初めはわからないことばかりで、上手に活用できないかもしれません。
システムのサポートの力を借りながら、DXについての知識と技術を着実に蓄えていくのがおすすめです。
建設DXを成功させるには、以下のポイントを意識しましょう。
DXを成功させるためには、現状の課題を明確にすることが大切です。
特に現場の意見は、実際に働く社員に丁寧なヒアリングを行って、問題を認識できるように心がけましょう。
会社が今どんな状態にあって、どんな課題を抱えているのかが明確にならなければ、DX化をしても意味がありません。
現状の課題を洗い出し、解決すべきポイントを把握することで、最適な問題解決の手段が見えてきます。
なお、DXを行う際はきちんと目的と方向性を定めておき、社員に説明できるようにしておきましょう。
目的が不明瞭なまま新しい物事を始めると、
現場にとってはよくわからないものを学習しなければならず、不満の温床となります。
会社全体でDXを行えるよう、現状の課題を明確にするのが成功のためのポイントです。
DXといっても、その種類は様々です。
コミュニケーションツールを例にすれば、Slackやchatwork、Microsoft teamsなどいくつもの種類が存在します。
この中で、自社にあうサービスを選んで導入することが大切です。
社風に合わないツールや不要なシステムは、無駄なコストとなってしまいます。
余計な出費をしないよう、導入前に必要なツールは何か考えておくことが大切です。
もっとも大切なポイントは、少しずつDXを行うことです。
一気にDXを進めようとすると、多くのシステムを導入するのにまずコストがかかり、現場も新しいシステムに対応しなくてはなりません。
結果、効率化どころかDXに対応するのに精一杯になってしまい、生産性が落ちることも考えられます。
小さな範囲からDXをしていって、少しずつ慣れながら変革していくようにしましょう。
実際に建設DXの成功事例を見ていきましょう。ここではDXの取り組みに成功した7つの事例を紹介します。
清水建設は、AR技術を活用した「Shimz AR Eye」というシステムを独自開発しました。
携帯端末で建設物の3Dデータを閲覧し、リアルタイムの映像と組み合わせることで現場の状況をひと目で把握できるシステムです。
施工管理では、複雑な構造の建設物や配管の確認業務が大きな負担となっています。
「Shimz AR Eye」を建築物に向けると、自動的に3Dデータとリアルタイムの映像が表示されるため、
確認業務を大幅に効率化することができます。
今後ますます複雑になっていくと予想される設備配管業務のサポートシステムとして、
「Shimz AR Eye」には大きな期待が寄せられています。
出典:清水建設株式会社https://www.shimz.co.jp/company/about/news-release/2021/2020060.html
鹿島建設では、現実空間を仮想空間にモデル化する取り組みを行っています。
羽田空港周辺の大型複合施設「HANEDA INNOVATION CITY」(通称「HICity」)での試みです。
空港周辺の現実空間をモデリングすれば、
空港内の各施設やバスの運行状況、施設内で使用しているロボットの稼働状況などを
すぐに把握できます。
この取り組みは、地域での連携を高めて、
あらゆる産業の交流機会を作り出すことを目的としています。
企業の利益だけでなく、地域全体の課題解決として大きな意味を持つのもDXの魅力のひとつです。
現実空間を仮想空間にモデル化するデジタルツインをエリアレベルで実現しています。
各施設や自律走行バスの混雑状況、施設管理スタッフやサービスロボットの稼働状況を可視化。
また収集したビッグデータをAIで解析することで合理的な施設運営をはかっています。
出典:鹿島建設株式会社 https://www.kajima.co.jp/news/digest/sep_2021/feature/01/index.html
熊谷組では、ダムの施工に用いられる骨材の大きさを自動で判別するシステムを開発しています。
トラックに積まれた骨材を2台のステレオカメラで撮影すると、
骨材とは、コンクリートやアスファルトなどを作るための砂利のことです。
大きさの異なる骨材が混ざってしまうと、決められた配合を守ることができません。
このような誤投入が発生すると、コンクリートやアスファルトの品質を保持できなくなってしまいます。
自動的に骨材の大きさを判別するシステムがあれば、誤投入や誤搬入を予防できます。
人力での作業の場合、ミスを100%防ぐのはほぼ不可能ですが、
機械はプログラムに従って動いてくれるので、分量を間違えることはありません。
この骨材粒径判別システムは、従来よりも効率よく、そして安全性の高いコンクリート製造を実現しました。
出典:株式会社熊谷組 https://www.kumagaigumi.co.jp/ir/management/dx/dx/index.html
平山建設では、働き方改革の一環としてDXに取り組んでいます。
具体的には、クラウドストレージを活用したデータの管理です。
工事に関わる書類や現場の写真をクラウド上に保存することで、
進捗管理の効率を向上させることができます。
テキストのやり取りも記録に残せるので、あとで確認するときにも効果的です。
協力業者のコミュニケーションにも活用できるので、お互いにストレスのない連携が可能となります。
このように、クラウドを活用した社内体制の確立により、
コミュニケーションや移動の問題を解決し、より働きやすい環境を構築しているのが平山建設の取り組みです。
これからDXを考えている小規模業者は、この事例をお手本にDXを取り入れてみてはいかがでしょう。
出典:平山建設株式会社 https://hirayama.com/dx_suishin.html
後藤組では、業務データを可視化するシステムのAI分析によって経営戦略を最適化するDXを行っています。
業務プロセスごとに目標を設定してリアルタイムに社員間で共有するシステムで、
「リアルタイム経営」と銘打った取り組みです。
全社員にタブレット端末を配布し、現場でデータを管理するシステムにアクセスすることができます。
属人化した経験やスキルに頼らずとも、
データに基づいて最適な判断を下せるようになることはその後の社員教育にも効果的です。
工事の安全性を高めつつ、業務効率化と経営戦略の立案が同時に行えるのは建設DXの大きなメリットといえるでしょう。
出典:株式会社後藤組 https://www.gto-con.co.jp/dx/
東急建設株式会社では、360度撮影できるカメラを活用して現場状況の把握を行っています。
初めは現場に設置したカメラでリアルタイムの映像を確認する方法を取っていましたが、
現場の映像を網羅的に映し出すためには相当数のカメラが必要になることや、
通信環境が悪いと鮮明な映像が映らないなど、数々の問題が発生していました。
そこで、360度撮影できるカメラを活用して、最小限のカメラ台数で現場をぐるっと見渡せる仕組みを作りました。
このとき使用したのは、「RICOH360 Project」というクラウドサービスです。
現場全体の把握ができるだけでなく、進捗の確認や施工後の状態を過去の画像から判断することも可能になりました。
出典:東急建設株式会社 https://www.tokyu-cnst.co.jp/company/strategy/digital_transformation/
建設DXにおすすめのソフト・サービスとして、以下の5つを紹介します。
monectは、経理関連の書類管理に特化したアプリです。
経理関係の書類を手軽に管理できることに加え、インボイス制度への対応や承認フローの作成など
手間のかかる作業を効率化するのに役立ちます。
「DXを取り入れたいけど、機械やシステムの操作に自信がない」という人でも
、担当者が丁寧に説明するので、安心してお使いいただけます。
導入にあたっては、まずは面談を行い、使い方について説明を行います。
導入や使い方についての説明会も開催しているので、興味のある方はぜひご参加ください。
SPIDER PLUSは、建設現場の図面作成や施工管理に特化したアプリです。
クラウドで進捗管理を行えるので、誰でも簡単にデータへのアクセスができます。
タブレット一つで現場の状況把握や写真撮影、記録などが行えるので、
本社と現場で往復する時間も削減できます。
導入は、App Storeから簡単にインストールできます。
使い方に関するお問い合わせは、電話や公式サイトのフォームから行ってください。
全社で導入することを検討している場合は、各支店や各支社への説明会も行っています。
興味のある方は相談してみるとよいでしょう。
Conne(コンネ)は、コミュニケーションの効率化に特化したクラウドサービスです。
社内・協力会社・顧客それぞれとのやり取りを円滑にすることで、効率よく業務を進められるでしょう。
特に優れているポイントは、使いやすさです。
PC操作に慣れていなくても、直感的に操作しやすい画面と操作方法でストレスなくサービスを利用できます。
見た目はSNSに近いので、若い世代の人も抵抗なく扱えるのが魅力的。
社外の人はメールアドレスを追加することで、ゲストメンバーとしてワークスペースに参加できます。
コミュニケーションのしやすさは他のサービスと一線を画すものがあるので、ぜひ検討してみてください。
https://conne.genbasupport.com/
ichimillは、GNSSデータの補正情報を活用した位置情報サービスです。
誤差は数センチメートル程度のもので、正確な位置を把握するのに役立ちます。
ichimillは、
ドローンに搭載して空撮の補助としたり、重機の自動運転をサポートしたりなどの使い方があります。
建設現場では重機の位置情報を把握して、工事の進捗を確認するのにも効果的です。
導入前に、1週間の無料トライアル期間が設けられています。
一度試してみてから、使い易ければ正式に導入する、という動きも可能です。
公式ホームページで資料をダウンロードできるので、興味のある方は見てみてください。
https://www.softbank.jp/biz/services/analytics/ichimill/
site(サイト)は、情報共有に最適なツールです。
案件ごとに顧客と現場資料を紐付けて保存できるので、データの一元化にも便利です。
チャット機能やスケジュール共有機能もあり、これまでになく情報共有を簡単に行えるでしょう。
siteの基本的な機能は、以下の3つです。
それぞれが連携しているので、シンプルな操作が可能です。
導入に関するサポートも手厚く、説明会や活用方法の提案、運用ルールの策定に3ヶ月間のサポートなどを行っています。
情報の管理がスムーズに行えれば、工事自体も滞りなく進行できるでしょう。
より円滑に業務を進めるために、siteの導入を検討してみてはいかがでしょう。