050-3000-0768
【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)
050-3000-0768
【受付時間】10:00~18:00(土日祝を除く)
2023/8/31
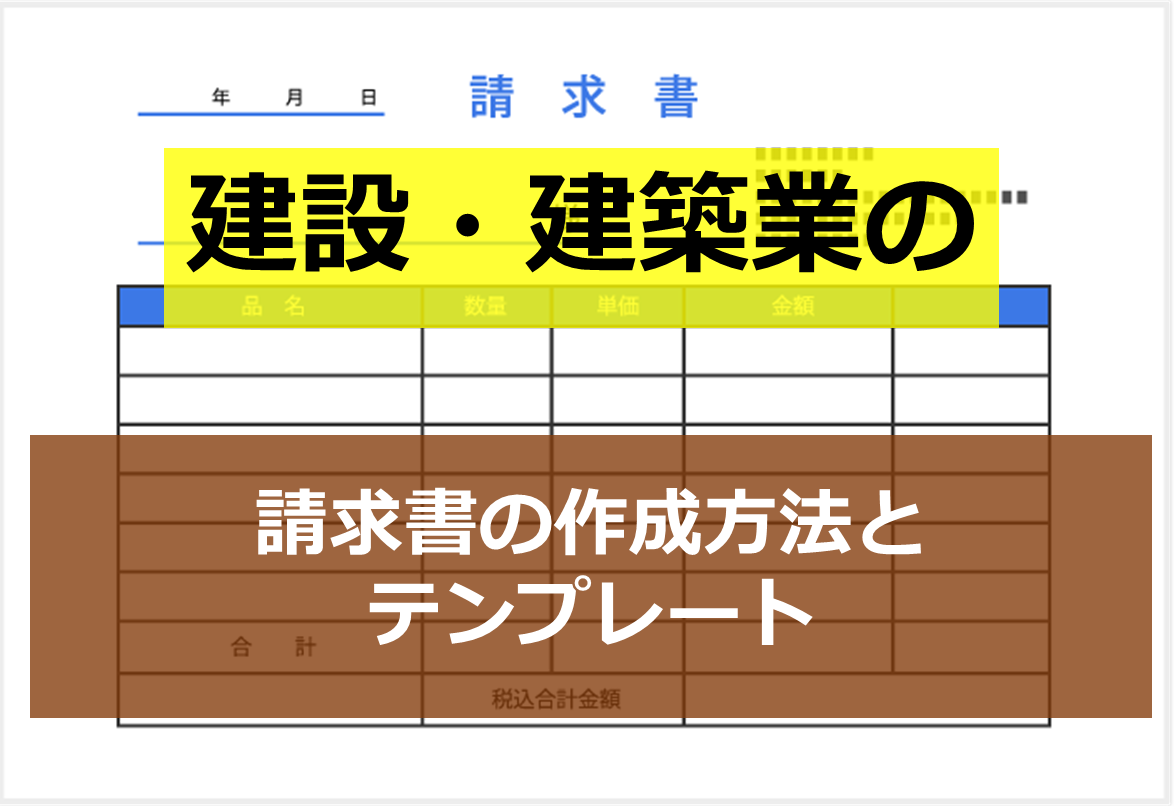
建設業の請求書は、他業種よりも特殊な部分が多いです。
そのため、書類の作成に頭を悩ませている担当者の方も多いのではないでしょうか。
請求書の作成は、テンプレートを活用すると便利です。一から作成するのではなく、
始めからできているものを使えば、その後も使いまわすことができます。
この記事では、建設業における請求書がどのような役割を持っているのか、
どのようなことに注意して記載・入力すべきなのかを解説します。
無料のテンプレートも配布しているので、ぜひご活用ください!
請求書は、取引先や顧客に向けて支払いを請求するための書類のことです。
料金が発生した場合、期日までの支払いを求める内容を記載します。
請求書の送付は、法的に義務付けられているわけではありません。
しかし請求書は支払いの金額を明確化し、支払い期日・期限も定義できるため、
無用なトラブルを避けるために取引の際の慣例となっています。
請求書は、
一般的に料金の金額と支払い期日・期限を明確にするという役割を持った書類ですが、
建設業においては請求書作成の意味合いが異なります。
建設業における請求書の役割と特徴を正しく認識しておきましょう。
ここでは、以下の論点について解説します。
まずは、建設業の請求書にどのような特徴があるのかを知っておきましょう。
他業種に比べて、建設業の請求書には以下のような特徴があります。
建設業の請求書は、他業種とは違い数回に分けて作成するのが一般的です。
本来請求書は、商品やサービスの受け渡しが完了したタイミングで作成します。
しかし工期が長引くことも珍しくない建設業の場合、
建設物の引き渡し後に請求書を作成する方式だとそれまで報酬を受け取れません。
工事に着手している間の資金管理や工事を始めるにあたって必要となる資金の用意は、
よほど経済的・金銭的に余裕のある会社でない限り簡単なものではないでしょう。
これらの問題をクリアするために、
建設業の請求書は工事の段階ごとに数回に分けて作成されるのです。
具体的にどうやって分けるのかというと、以下の区分で請求書を作成します。
多くの場合、工事の着工前の段階で、
発注者から建設業者などの受注者に対し支払われるお金のこと。
総工事代金の10~30%の金額が支払われます。
建設業者も、資金が無ければ工事を進めることが出来ないので、
その資金に充てられることが多いです。
工事請負契約に基づいて、建物引渡し前に支払われる代金の一部を指します。
特に工期が1年以上に及ぶような工事の場合は、中間金を複数回請求することもあります。
工事に必要な費用を事前に請求する、いわば「前借り」のようなシステムですが、
工事を着実に遂行するために必要です。
注文住宅の場合だと、
上棟時に支払われることが多いため、上棟金とも呼ばれることがあります。
工事が完了し、建物が引き渡される際に施主が建築業者に支払う残りのお金のことです。
着工金や中間金とは異なり、
工事請負契約者に記載された金額とは異なる場合があるという事をお忘れなく!
建設業のもう一つの特徴として、人件費の請求が複雑であることが挙げられます。
特に規模の大きい工事のとき、現場で仕事をする人の数も多くなります。
そのような場合に請求する人件費の項目として、「人工費」の項目が設けられています。
人工費とは、1日仕事をしてかかる人件費のことを指します。
元々は職人の工賃を計算するための項目でしたが、
現在は工事に関わるすべての人員の人件費を計算するための項目となっています。
人件費は、時間ではなく1日単位で計算します。
建設会社によって1人工がいくらなのかが異なりますし、職業によっても人工費の相場は異なります。
建設業の請求書は、他業種と異なる特徴や側面を持っています。
もっとも大きな違いは、工事を段階的に分けてそれぞれで請求書を発行することです。
建設業の場合は、工事の規模によって工期が変動する性質上、
完成したあとで請求書を送るのは難しくなってしまいます。
特に費用の面で、大規模な工事を行うときは人員や重機も十分な数を確保しなければならず、
この代金を捻出するのに苦労します。
工事が始まる前に、「着手金」という形で請求書を送ったり、
工事の途中に「中間金」という形で請求書を送ったりすることも、建設業では珍しくありません。
このように数回に分けて請求書を作成することには、
工事の途中でも進捗状況を確認しながら支払いを進められること、
工事関係者とのコミュニケーションや報告の機会が増えることにより
認識のすれ違いを防げることなどのメリットがあります。
また、請求書を複数回に分けて作成することには、
直接話し合う機会が増えれば、工事の進捗に関する認識のズレも抑えられるでしょう。
請求書は代金の支払いを求めるためだけの書類ではなく、
お互いの状況を把握しながら工事を円滑に進めるための進捗管理シートのような役割も担っているのです。
結果的により品質の高い工事ができるようになります。
請求書の作成方法・書き方には、主に3つの方法があります。以下の3つです。
請求書の書き方には、これといって決まったやり方があるわけではありません。
そのため、もっともやりやすい方法を採用することが大切です。
とはいえ、電子書類の保存要件の改正などもあり、
電子化の導入を考えている企業も少なくないでしょう。
それぞれの作成方法を把握して、どのやり方が自社に合っているのかを考えてみてください!
請求書は、文房具店や100円均一で市販のフォーマットを手に入れることができます。
PC作業が苦手な人の場合、こちらの方法で請求書を作成していることも多いのではないでしょうか。
市販のフォーマットは、手軽に手に入り、作成が簡単・シンプルです。
手書きという性質上、アナログな手法に慣れている人は親しみやすいでしょう。
しかしその反面、手書きでは計算も自分で行う必要があります。
清書の段階でこのようなミスをしてしまえば取り返しがつかず、
新たな用紙に書き直しとなってしまいます。
このようなミスを避けるためには、パソコンを用いて正確に記述と計算を行うのがおすすめです。
加えて、書類の電子化が義務化されましたので、
紙の書類や文書から離れて電子化していく動きは検討すべきであるのではないでしょうか。
請求書作成の代表的な方法が、WordやExcelなどのOffice系ソフトの活用です。
特にExcelは関数式や計算式を利用できるので、簡単に請求書の作成を進められます。
レイアウトの調整も自在なので、より見やすい請求書を作るのに適しています。
このようなExcelなどのソフトを活用すれば、経理担当者の負担軽減につながります。
書類作成を効率化できれば、空いた時間で他の作業を行うなど、会社全体の効率化も図れます!
WordやExcelなどのソフトで請求書を作成するのであれば、
テンプレートを利用するのがおすすめです。
テンプレートとは、あらかじめ作成されたフォーマットのことです。
ひとつダウンロードしておけば、
その後は元ファイルをコピーすることで何回でも同じテンプレートを使うことができます。
項目はすでに作成されているので、それにしたがって記入していけば問題ありません。
とはいえ、Excelで請求データの集計を行うのは簡単なことではありません。
ある程度操作に慣れた人や知識がある人が扱わない限り、有効活用するのは難しいでしょう。
関数など、Excel自体の操作方法をよく知っていないと、操作面で苦戦する可能性が高いからです。
また、もしExcelを扱える人が少ない場合、
その人だけが操作できる状態(属人化)になってしまうケースも少なくありません。
管理面の効率化を図るのが目的であれば、経理部門の社員全員が同様にExcelを扱えるようにしておき、
作成したファイルは月次や顧客ごとのフォルダを作成して管理しておきましょう。
なお、Officeソフトは主にWindowsで使用されるソフトです。
オンラインで管理したい場合はGoogleスプレッドシートを活用するのがおすすめです
請求書作成にもっともおすすめの方法は、請求書作成システムの活用です。
ExcelやWordなどのソフトとは異なり、一般的にわかりやすい操作のみで請求書を作成することができます。
システムを利用する人間が全員同じように操作できるので、引き継ぎも簡単です。
二重請求や記入漏れなどのミスも格段に防止しやすくなります。
ただし、請求書作成システムの導入には費用がかかります。
費用相場は安価ではありませんが、
請求書作成に関しての業務負担を低減できるのは無視できないポイントです!
なお、建設業に特化した場合のシステムでは、
工事台帳や作業員の日報から請求書の作成ができる機能を持つものもあります。
取得したデータはシステム内で管理され、工事の内容と請求データの比較がしやすいことが特徴です。
経営戦略を立てるためのデータとしても活用できるので、
請求書を作成するためでなく、会社がより成長するためのツールとしても利用できます。
請求書作成システムについては、この記事の後半部分でも触れています。
詳しく知りたい方はそちらをご参考ください。
まずは請求書に記載するべき項目について解説します。
請求書にはフォーマットはありません!
ここで紹介する基本的な項目が入っていれば形式は問題ありません。
請求書に記載する項目は、以下の通りです。
請求書には、請求する相手の宛名を記載します。請求先の会社名や誌名などです。
宛名は省略せず、正式名称を用います。
例えば株式会社なら「〇〇会社(株)」などとせず、「〇〇株式会社」と記載します。
請求書には、発行者の情報も記載します。要するに自社のことです。
会社名や会社所在地(個人の場合は個人名や住所)を記載し、会社の印鑑または担当者の印鑑を捺印します。
請求書には、取引内容の詳細を記載します。
具体的には以下の項目です。
取引内容を記載するときのポイントは、できるだけ内容を明確にしておくことです。
取引相手が理解しやすいよう配慮して記載しましょう。
特に数量の項目では「一式」というように略式で記載する場合もありますが、
このような書き方をしてもよいのはある程度関係性ができている取引相手の場合のみです。
品目は細かく記載しないと取引先の混乱を招き、トラブルの原因にもなるかもしれません。
また金額部分は税抜きの価格を記載し、
値引きがある場合は「−」「▲」「△」など記号を使ってマイナスを表記します。
取引内容に記載した金額をすべて合計して、税抜きの総額を記載します。
小計額を記載したら、請求する金額を表示します。
小計の金額に消費税を足したものが請求する金額となります。
源泉徴収をする場合は、小計と消費税の合計から源泉徴収額を差し引いた金額を記載します。
請求した金額をどこに振り込んでもらうか、という情報も必要です。
振込先の
口座情報は以下のように記載します。
上記の情報は最低限必要なものですが、
余裕があれば銀行コードと支店コードも記載しておくとミスを防ぎ、また印象が良くなります。
口座名義はカタカナで書くのがルールなので、気をつけましょう。
口座情報に誤りがあると、支払額を受け取れません。
ミスなく記載できているかは入念にチェックしておく必要があります。
請求書には番号をつけておきましょう。
取引先から請求書に関する問い合わせがあった場合に、お互いに請求書を探しやすくなります。
特に取引を何度も行う相手先の請求書には、通し番号を振っておくのがおすすめです。
発行年月日は、基本的に作成した年月日を記載します。
ただし、取引先では発行年月日が決められている場合があるので、
相手に合わせて記載するようにしましょう。
備考欄には、補足情報を記載します。
代金の手数料は自社が負担するのか相手が負担するのか、
振り込みの期日はいつまでなのかなどを記載しましょう。
請求書作成には、3つのポイントがあります。それは以下の通りです。
建設業では、人件費の計算に「人工(にんく)」の考え方を使用します。
人工とは、1人の作業員が1日働いたときの報酬の単位のことです。
例えば3人の作業員が5日間働いた場合、3人×5日間で15人工となります。
人工費という項目で請求できるのは、請負契約以外の場合です。
例えば一人親方が建設会社から業務を委託された場合に、人工費として請求できます。
注意すべきは、
請負契約の請求書には「人工費」や「人工出し」という項目を用いると法に触れていしまう場合があります。
現場に労働者を派遣した場合、
労働者派遣法第4条8労働者派遣事業の許可制)および第24条(偽装請負の禁止)に関連する問題が
生じる可能性があります。
参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
人工費は、工事原価管理の観点からすると非常に大事な考え方です。
そのため、作業代金を請求する場合は工事代金に含めて請求することが一般的な手法です。
ただし、工事代金の内訳についてはいきなり請求するのではなく、
取引相手にきちんと説明しておくことも忘れないようにしましょう。
請求書の文言では専門用語を使用せず、一般的な言葉を使用しましょう。
専門用語を使って相手に伝わらなければ、不快にさせてしまう可能性があるからです。
請求書を確認する担当者が建設業界に詳しいとは限りません。
会社によっては、経理担当者や税理士など、
現場を訪れる機会が少ない人が請求書の確認業務をしていることも珍しくありません。
そのような人が専門用語だらけの請求書を見たとき、
スムーズに確認作業が進まないことは容易に想像できるでしょう。
さらに、人によっては理解しにくい請求書が送られてきたことで苛立ったり、
不信感を抱いたりすることもあります。
無用な軋轢を生まないためにも、
請求書に専門用語を使用するのはできるだけ控えましょう。
親切にわかりやすく作られた請求書を見れば、丁寧に説明しようという気持ちも伝わるでしょう。
このような配慮を行うことは、良好な関係構築につながります。
どうしても一般的な言葉に置き換えるのが難しいときは、注釈や備考欄を活用しましょう。
工事代金の請求方法は、事前に請負元に確認しておくことが重要です。
あらかじめ決めておくと、代金の未払いや支払いの遅れなどのトラブルを回避できます。
決めておく要件は、以下の通りです。
特に工期の長い工事の場合は、着手金や中間金などの形で代金を請求することが一般的です。
建設業に知見のない顧客との取引をするときは、
このような仕組みについて事前に説明しておくとよいでしょう。
顧客がきちんと理解できるように説明しておくことも、
トラブルを避けるための大事なポイントです。
2023年10月から、インボイス制度が開始されました。
請求書の作り方や書き方、保存方法が変わったので、ここで解説します!
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、
請求書の作成と保存の方式が変わりました。
「適格請求書」という所定の書類を使用しないと仕入れ税額控除を受けられません。
適格請求書を発行できるのは課税事業者に限られ、免税事業者は対応を迫られています。
といっても、新しい書類を作成するわけではありません。
従来の請求書に、新たに記載すべき項目が増えただけ、という認識で問題はありません。
インボイス制度に対応した請求書に記載する項目は以下の通りです。
上記の情報を明記することで、インボイス制度に対応できるようになります。
インボイス制度への対応にあたり、3つの注意点があります。
消費税率には、8%と10%の区分があります。
端数が異なる複数の処理があるときは、ひとつのインボイスにつき1回の処理が認められています。
税率ごとに区分した消費税額は、以下の端数処理の事例(OK事例)のように、
ひとつのインボイスにつき、1回ごとの端数処理となります。
端数処理が認められるか知りたい場合は、
国税庁の税務相談チャットボットで質問できるので活用していきましょう。
インボイス制度では、
インボイスQ&A・問56(一定期間の取引をまとめた請求書の交付)に記載のように、
月締め請求書と個々の納品書を合わせて1つのインボイスにすることが認められています。
また、以下の取引ではインボイスの交付義務が免除されています。
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機関特例」といいます。)
② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(以下「自動販売機特例」といいます。)
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
引用:国税庁|インボイスとは
近年では、書類を電子化する動きも促進されています。
ただし電子データを保存する際は、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があるので要注意です。
インボイス制度と電子帳簿保存法に対応するためには、書類作成・保存システムの導入が必須です。
厳密には人力でも対応自体は可能ですが、
現実的に考えると人手に任せて書類の作成・管理、保存業務を行うのは無理があります。
システムの導入には費用もかかりますが、
長い目で見たときの費用対効果は非常に大きいといえるでしょう。
請求書を作成するときは、テンプレートを使うのがおすすめです。
以下のリンクから建築・建設業向けのテンプレートがダウンロードできるので、ぜひ活用してください。
請求書発行システムとは、請求書の作成を効率化するためのシステムです。
導入すれば、請求書の作成における管理面の負担を一気に減らせるでしょう。
電子化が主流となり、
インボイス制度への対応も急がれる今の時期では、もはやシステムの導入は必須ともいえます。
この項目では以下のことについて解説します!
ぜひ請求書作成システムへの理解を深めていってください。
請求書発行システムには、以下のような機能があります。
請求書を作成する業務の効率化や管理・セキュリティの向上などを考えると、
利便性の高い機能が揃っています。
請求書発行システムには、以下のようなメリットがあります。
ポイントとなるのは、やはり請求書に関連する業務の効率化です。
これまで手作業で行っていた業務をシステムが一元化してくれるおかげで、
大幅な効率化を期待できます。
社内の全員が同じシステムを使うことで、
コミュニケーションや手作業によるミスも減らせるでしょう。
請求書発行システムには、「クラウド型」「オンプレミス型」の2種類があります。
基本的におすすめなのはクラウド型です。
インターネット環境があれば社外からでもアクセスでき、費用も比較的安いというメリットがあります。
オンプレミス型は自社のサーバーにシステムを構築する形で導入するもので、
保守や運用コストがかかることが難点です。
しかし自社のやり方に合わせて自在にカスタマイズできるという側面も持っています。
請求書発行システムは、以下のように選べばミスマッチも少なくなります。
基本的には上記5項目の視点で選ぶのがおすすめです。
特に重要なのは、電子帳簿保存法とインボイス制度への対応ができるか、という点。
法改正に迅速に対応できることは、今後大きく役に立つでしょう。
請求書発行システムについての詳細がわかったところで、おすすめのシステムを紹介します。
建設業の請求書作成におすすめのシステム3選を紹介します!
興味のあるシステムを探してみてください。
monectは、建設業の経理業務全般を効率化できるシステムです。
インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しています。
monectで利用できる機能は以下の通りです。
料金は1ユーザーにつき月額550円から利用できます。
さらに導入に関しては面談での説明に加え、社内テストまで一緒に行ってくれるのも魅力的。
協力会社向けのセミナーも開催されているので、
導入・運用についての不安を解消できるのもおすすめのポイントです。
monectはこちら
楽楽明細は、帳票の発行を効率化してくれる請求書発行システムです。
帳票データをCSVやPDFデータのままアップロードすることで、帳票を発行できます。
楽楽明細の特徴は以下の通りです。
電子帳簿保存法の改正要件にも対応しているので、安心してシステムを利用できます。
帳票の発行方法も多様で、ニーズに合わせて最適なデータ管理を行えるでしょう。
楽楽明細のシリーズである「楽楽販売」「楽楽精算」などと組み合わせると、
より利便性高く活用できます。
楽楽明細はこちら
マネーフォワードクラウド請求書は、
同社会計ソフトと連携して活用できる請求書発行システムです。
毎月の自動作成機能や売上レポートの作成機能など、嬉しい機能が豊富に搭載されています。
マネーフォワードクラウド請求書の特徴
マネーフォワードクラウド請求書の強みは、請求書ごとの特記事項を保持できることです。
この機能があれば、ミスを未然に防ぐ体制も作りやすいでしょう。
さらに入金の状態もすぐにわかるので、請求漏れも防げます。
電子帳簿保存法にも対応しています。
マネーフォワードクラウド請求はこちら
建設業の請求書は、他業種に比べて特殊な点が多いです。
特に着手金や中間金を請求することや、
人工計算を用いて人件費を請求することなどは、難解に思えるのではないでしょうか。
しかし、請求書の作成方法を正しく理解していないと、思わぬ損失につながるかもしれません。
そのような事態を避けるためにも、請求書作成のポイントは正しく認識しておきましょう。
そのうえで、ある程度はシステムに任せることも大切です。
請求書発行システムの重要性を考えて、導入を検討してみてはいかがでしょう。